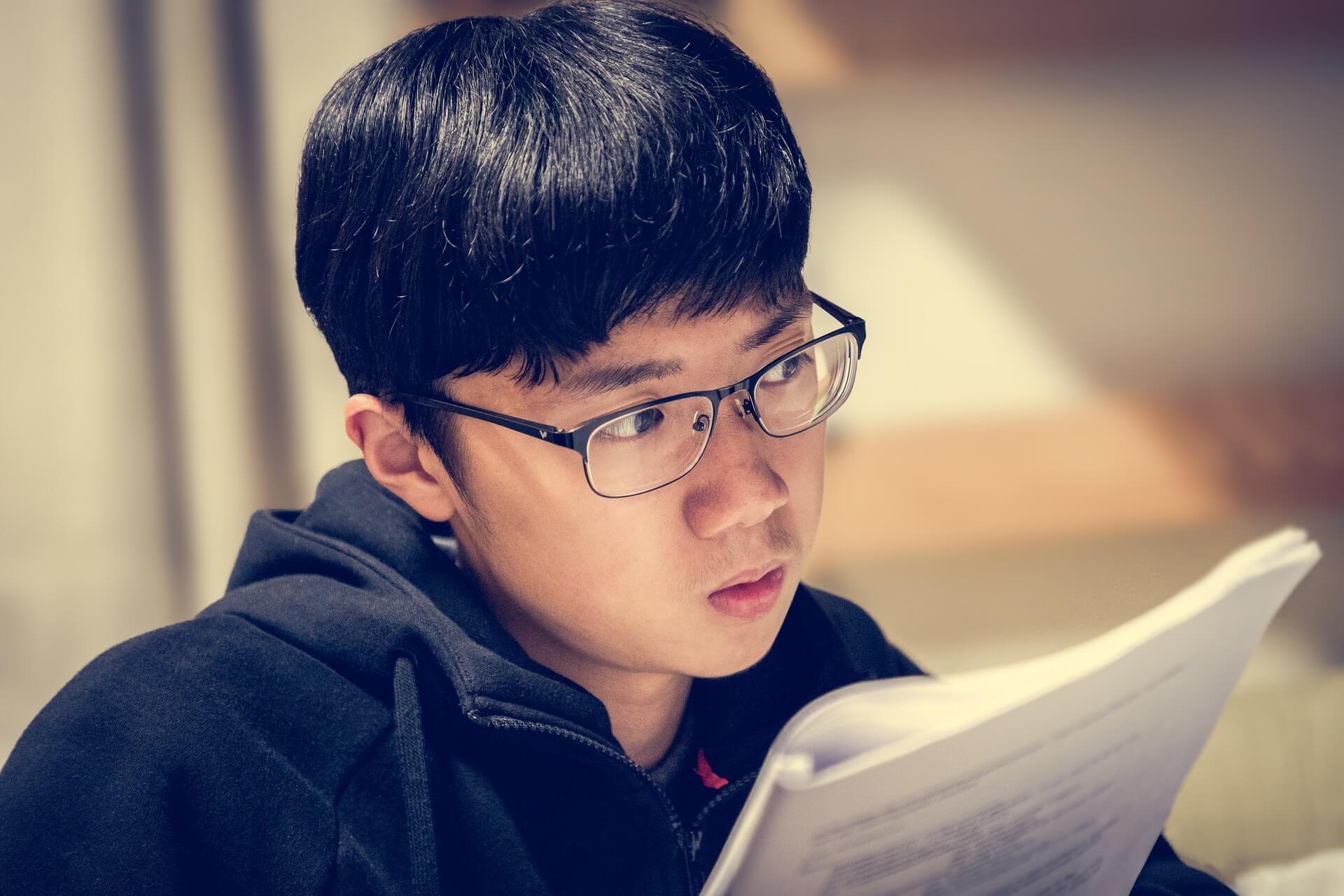- 正式な英語論文は、一定の形式に則って書くことが大切です。
- この記事では、論文やレポートの書き方の基本を、例文を示して解説します。
- 臨床心理学の研究に関する英語も紹介します。興味のある人はお読みください。
英語論文をどう書くか
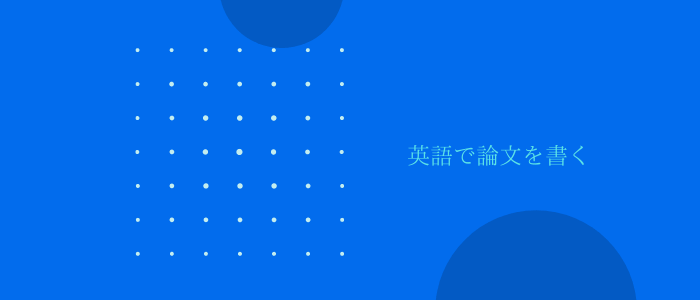
英語で論文やレポートを書くとき、どうしたらいいでしょう?
まず、書いていく際に、私が大事だと思うことをあげておきましょう。
- テーマの絞り具合。広げたり狭めたり。タイトルは内容がはっきりわかること。
- キーワードを集める。それに関する重要文献をおさえる。最近の話題を入れる。
- 資料を集める。国会図書館、地方図書館の利用も。執拗な調査能力。
- 研究の意義と目的がはっきり書かれている。
- 読みやすい文に。用語定義と引用、概念の対比、理由の説明。
- 抽象的な部分には例示を入れる。
- 内容を整理する。(すっきりした論理展開、位置や順番を考慮)
- 情報の取捨選択をして、異質なものを入れず純度を高くする。
- 一般的な言葉なのか、独自の言葉なのかを明記。謙虚で配慮のある表現。
- 文の主語を明確にする。主体の側なのか、客体の側なのか。
- 「~とは何であろうか」など疑問文を入れる。(みんなが思うような重要な問い)
- 内容や語句の重複は回避する。前作の内容との重複も避ける。
- 研究手続きに問題点はないか。
- 他人の目、時間を置いた目でチェック。
- 謎の部分、余計な部分は次の論文に回す。背伸びせずわかることだけ書く。
- 書いておけば、投稿先はどこかに見つけられる。投稿先の書式の規定を守る。
ただ、はじめから完璧に書こうと思わずに、修正を前提に書き始めることが大切です。論文の場合、何度も「推敲=練り直し」をすることが決定的に重要です。
いきなりすべてのルールを覚えなくていいです。まずは基本を押さえましょう。
ここでは、英語論文初心者をおもな対象として、基本的な注意点をまとめます。
書き言葉を使う
会話やブログとは違い、論文はフォーマルな文章です。書き言葉を使います。
口語表現を使うと、品格のない、なれなれしい雰囲気が出てきます。
論理の展開が自然だと、とても読みやすい文章になります。接続詞・接続表現は、論理の道筋を示すために重要です。論文では and, but, so などで文章を始めないことです。もし使うのであれば moreover, however などを使うようにします。
他にも覚えておきたいものをある程度紹介しておきます。
therefore(したがって), thus(このようにして), although(だけれども), not only ~ but also ~(~だけでなく~も), in the same way(同じように), as a result(結果として), it follows that(当然~ということになる), this suggests that(このことは~を示唆している), for this reason(この理由のために), on the other hand(他方で), on the contrary(逆に), conversely(逆に), despite(にもかかわらず), nevertheless(にもかかわらず), nonetheless(にもかかわらず), hence(それゆえ), correspondingly(それに応じて), consequently(結果的に), alternatively(代わりに)
接続詞・接続表現は、この記事の例文にもいくつか入れておきました。
ちなみに、接続詞を詳しく解説した記事はこちらです。
一人称を多用しない
客観的な論文では、 I や We などの一人称は避けるべきとの助言もあります。使ってもよいとの意見もあります。ここは、考え方がわかれるところです。
We discuss ~ などは,筆者と読者を想定して使われることがあります。
たしかに、 I を多用する人は多いようです。読む側にはワンパターンに聞こえます。
その場合は、名詞を主語にして無生物主語を使えば、英語らしい文になります。
文章はわかりやすく
だらだらと書かない
冗長あるいは複雑な表現を、簡潔な言い方に変えます。
たとえば、 It is clear that ~ は Clearly, と書きます。関係代名詞は入れ子で使いません。
曖昧さ、余韻は不要
論文では文学的表現は必要ありません(もちろん、文学などを扱った論文は別)。
意図した内容が明確に伝わるように工夫しましょう。
could, would, might, maybe などの曖昧表現は、使わないほうがよいでしょう。数値を添えて表現すると明確に伝わりやすいです。
受動態を減らす
受動態の多用は、文章を複雑にします。客観的に書く目的でそれを使うことはあります。
ただ、日本人の英作文では受動態が使われがちです。
SVOで簡潔に表現しましょう。
論文の検索方法
Google scholar はグーグルの検索エンジンの一つです。英語のキーワードを入力すれば、英語の論文や学術誌を検索できます。
通常の Google の検索エンジンと同様、複数の語句でも検索できます。
論文やレポートを書く人にとっては、便利なサービスです。
論文の一般的構成
一般的な論文の構成はだいたい次のようになっています。
ジャーナルによって違いもあります。また、各項目ごとに一定の書き方のルールや慣行があります。この記事ではそこまでは触れません。
- Title タイトル
- Authors 著者
- Affiliations 所属
- Keywords キーワード
- Abstract 要旨
- Introduction 序論
- Materials and methods 実験材料および方法
- Results 結果
- Discussion 考察
- Conclusions 結論
- Acknowledgements 謝辞
- Reference 参考文献
- Appendices 付録
論文の頻出表現
ここでは、項目ごとに英語の論文で実際に使える表現を紹介します。
ちなみに、 that 節を使った意見の述べ方をまとめた記事もあります。
こちらは具体例・典拠を示すときの定型表現をまとめた記事です。
タイトル
タイトルのつけ方の例を紹介しておきます。
Analysis of A Aの分析
Aspects of A Aの諸相
An empirical research for Aing Aするための実証的研究
An experimental study of A Aの実験的研究
Case study on A Aの事例研究
Evaluating the impact of A Aの影響の評価
The effect of A on B AがBに及ぼす影響
The role of A in B BにおけるAの役割
Classifying A based on B Bに基づいたAの分類
Comparative study of A and B AとBの比較研究
Therapeutic relationship between A and B AとBの治療関係
Predicting A from B BからAを予測する
What are the determinants for A to do B? AがBをする決定要因は?
目的
This article reviews the history of research on this topic.
訳 本稿では、このテーマに関する研究の歴史を振り返る。
This paper illustrates the importance of the latter.
訳 本稿では、後者の重要性を説明する。
The aim of this study is to draw a distinction between A and B.
訳 この研究の目的は、AとBの区別をつけることです。
draw a distinction は distinguish 一語で簡潔に表現できます。
Likewise, a detailed study was conducted to confirm the validity.
訳 同様に、妥当性を確認するために詳細な調査が行われた。
参照・言及
It has been reported that this new method is superior to the old one.
訳 この新しい方法は、古い方法よりも優れていると報告されています。
Studies have indicated that ~ だと、「研究は~を示唆してきた」。
Negative feedback will be referenced in the following section.
訳 否定的な意見については、次のセクションで言及する。
同様の書き方で、たとえば In the following section, ~ will be discussed であれば、「次のセクションでは~を議論します」となります。
Therefore, it is important to mention issues such as a clinical trial.
訳 したがって、臨床試験などの問題に言及することは重要である。
問いと答え
The researchers have posed a fundamental question regarding those findings.
訳 研究者たちは、これらの調査結果について根本的な疑問を投げかけている。
Responses to possible questions are as follows.
訳 想定される質問に対する回答は以下の通りである。
比較検討
This surpasses them in terms of both quality and quantity.
訳 これは、質・量ともにそれらを上回っています。
Compared to the outcome of the former survey, this led to a unique conclusion.
訳 以前の調査結果と比較すると、これはユニークな結論となった。
分類・差異
The subjects are divided into three categories.
訳 対象は3つのカテゴリーに分かれている。
From a strict point of view, it is not possible to distinctly categorize all the indicators.
訳 厳密な観点からは、すべての指標を明確に分類することはできない。
The observation periods range from days to months.
訳 観測期間は数日から数ヶ月に及ぶ。
Based on their study, the minor distinction between the two concepts can be ignored.
訳 彼らの研究に基づけば、この2つの概念の細かな違いは無視できる。
This case differs from the previous ones.
訳 今回のケースは、これまでのケースとは異なる。
関連・因果
Table A indicates that the former is strongly associated with the latter.
訳 表Aは、前者が後者と強く関連していることを示している。
This discovery is closely related to the experiment conducted by him.
訳 この発見は、彼の実験と密接に関係している。
This phenomenon is consistent with a theoretical explanation.
訳 この現象は、理論的な説明と一致しています。
The value increased as the density decreased.
訳 その値は密度が低くなるにつれて大きくなった。
This equation is correct as long as the above hypothesis is correct.
訳 上記の仮説が正しい限り、この式は正しい。
The effectiveness of the method depends on the circumstances.
訳 この方法の有効性は状況によって異なる。
The process is comparable to the typical development of the brain.
訳 その過程は、典型的な脳の発達に相当する。
It follows that the other unknown factor influenced the subject’s behavior.
訳 したがって、もう1つの未知の要素が被験者の行動に影響を与えたということになる。
重要性
It is crucial to apply this concept derived from each example.
訳 それぞれの例から導き出されたこの概念を応用することが重要である。
This method is essential for the scientific handling of raw data.
訳 この方法は、生データを科学的に取り扱うために不可欠である。
The discovery is considered a breakthrough that was the first significant step in the field.
訳 その発見は、その分野での最初の重要な一歩となる画期的なものと考えられている。
Great emphasis has been placed on the experiment’s results, which were obtained through psychological tests.
訳 心理テストによって得られた実験結果が重視されている。
エビデンス
In other words, evidence needs to be gathered.
訳 つまり、証拠を集める必要があるのです。
It is widely acknowledged that his inference is based on facts to some extent.
訳 彼の推論はある程度事実に基づいていると一般的に認められています。
図表
Refer to Figure 3 to observe the evolution of the phylogenetic tree.
訳 系統樹の進化を見るには、図3を参照されたい。
The table below shows the changes in main indicators.
訳 下表は、主な指標の推移を示したものである。
ちなみに、ものごとの増減・変化を表す英語はこちらです。
結論・結果
An unexpected consequence resulted from an incorrect procedure.
訳 誤った手順により予期せぬ結果が生じた。
A cause B は「AはBの原因である」、A contribute to B は「AはBに貢献する」、A bring about B は「AはBをもたらす」、A lead to B は「AはBにつながる」。
In conclusion, this serves as a perfect example.
訳 結論として、これは完璧な例となる。
However, it is still uncertain whether this conclusion applies to all cases.
訳 しかし、この結論がすべてのケースに当てはまるかどうかはまだ定かではない。
The results support the new idea presented in the previous thesis. However, further surveys are necessary to draw a firm conclusion.
訳 この結果は、前論文で提示された新しいアイデアを支持するものである。しかし、確固たる結論を出すためには、さらなる調査が必要である。
研究に関する英語:臨床心理学の例
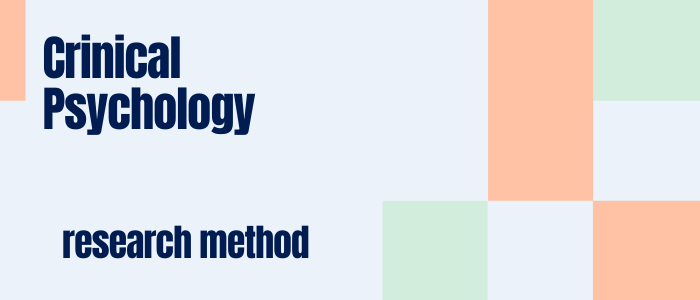
臨床心理士のおもな仕事の一つに「臨床心理学的研究」があります。
そこでは、実験・調査・面接・観察などのキーワードが登場します。
基本ワードを含む英語の例文を見ていきましょう。
参考資料 :
- 厚生労働省 e-ヘルスネット 健康用語辞典
- アメリカ心理学会 American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology
- 心理学 東京大学出版会
- 公認心理師・臨床心理士大学院対策 鉄則10&キーワード100 心理英語編 講談社
調査 Surveys
Psychologists may conduct surveys to make large-scale observations. A questionnaire is often used. Moreover, They can use psychometrics that tells us elaborate information about the person’s mind.
訳 心理学者は、大規模な観察のために調査を行うかもしれません。アンケートがよく使われます。また、人の心について精緻な情報を示してくれる心理測定法を用いることもあります。
questionnaire は「アンケート・質問紙」、psychometric は「心理測定法」です。心理学の主要な研究法は実験法・調査法・面接法・観察法があります。
統計的仮説検定 Testing statistical hypothesis
If the experimental group and the control group has a statistical significance, it follows that the result of the research could not have happened by chance. This is shown by the testing statistical hypothesis.
訳 実験群と対照群が統計的に有意であれば、その研究結果は偶然では起こり得なかったことになります。これを示すのが統計的仮説検定です。
experimental group は「実験群」、control group は「統制群」、statistical significance は「統計的に有意」です。実験群の得点平均と統制群の得点平均の差が誤差の範囲内かどうかを、実験者は判定する必要があります。
相関係数 Correlation coefficients
We often use correlation coefficients to measure how strong a relationship is between two variables. We know several types of correlation coefficients, but Pearson’s is the most popular.
訳 2変数の間にどれだけ強い関係があるかを測るのに、相関係数をよく使います。相関係数にはいくつか種類がありますが、最も一般的なのはピアソンのものです。
variable は「変数」です。単に相関係数と言うとき、普通はピアソンの積率相関係数のことを指します。相関係数とは、2つの変数間の関係の強さと方向性を表す、1~0~-1の範囲の数値のことです。
主効果と交互作用 Main effect and interaction
The main effect is defined as the effect of one independent variable on the dependent variable. The interaction occurs when the effect of one independent variable depends on the value of another independent variable.
訳 主効果は、1つの独立変数が従属変数に及ぼす効果と定義されます。交互作用は、ある独立変数の効果が別の独立変数の値に依存する場合に生じます。
independent variable は「独立変数」、dependent variable は「従属変数」です。 分散分析(analysis of variance; ANOVA)で、主効果はそれぞれの独立変数がそれぞれの従属変数へ与える単純効果のことをいいます。交互作用とは独立変数を組み合わせた場合に特有の複合効果のことです。
双子研究 Twin study
Twin study is a research method that utilizes twins. We can assess the influence of heredity and environment by comparing the characteristics of identical and fraternal twins.
訳 双子研究とは、双子を利用した研究手法です。一卵性双生児と二卵性双生児の特徴を比較することで、遺伝や環境の影響を評価できます。
heredity は「遺伝」です。environment は「環境」です。identical and fraternal twins は「一卵性と二卵性双生児」です。一卵性双生児どうしの遺伝子は100%同じですが、二卵性双生児どうしだと50%しか同じではありません。生活環境が同じだとして、ある性質の相関が一卵性双生児では高いのに二卵性双生児では低い場合、遺伝の影響が強いことが示唆されます。
参加観察 Participant observation
Participant observation is a technique of field research, by which an observer studies the real life of a group by sharing in its activities. This is also used in anthropology and sociology.
訳 参加観察とはフィールドリサーチの手法の一つです。観察者が集団の活動に参加して、その集団の実際の生活を調査するものです。人類学や社会学でも用いられます。
field research は「現場研究・野外研究」のことです。自然な状況で、人々と交流しながら観察・理解をしていく研究方法です。人類学 anthropology の研究方法は、初めは文献研究が多かったのです。しかし、現在の主流はフィールドワークになっています。
事例研究 Case study
A long time ago, case studies are often considered as being less scientific than large-scale studies. But recently, case studies have become a regular research method that gives us invaluable information.
訳 昔は、ケーススタディは大規模な研究に比べて科学性に欠けると思われがちでした。しかし最近では、ケーススタディはきわめて貴重な情報を与えてくれる正統派の研究手法となっています。
臨床心理学では、事例研究が重視されます。臨床事例の経過報告だけでは事例研究とは言えません。その事例から新たな理論や仮説を導き出す必要があります。
研究倫理 Research ethics
Research ethics should be observed. For example, researchers must inform all participants of the details including the research objectives, and must obtain the consent of participants in writing.
訳 研究倫理を守らなければなりません。たとえば、研究者は全参加者に研究目的などの詳細を伝え、書面で同意を得なければなりません。
研究倫理とは、研究者が研究活動を行うにあたって持つべき倫理観のことです。研究の「不正行為」を犯さないためには、研究者はインフォームド・コンセントや個人情報保護などに努めなければなりません。
豆知識
文章の説得力とは…
supporting evidence
意味 裏づける証拠、傍証
He added supporting evidence at the end of the section.
彼はセクションの最後に裏づけの証拠を加えた。
根拠・理由を示すことは大切ですね。
関連性の高い記事
まとめ
論文は内容もさることながら、言葉を選び、きちんとした形式に則って書くことも重要です。
口語的、一本調子、冗長性などの特徴が顕著だと、読者は読む意欲を失うかもしれません。
推敲を重ねて、納得がいくまで仕上げたいものです。
さらに勉強したいあなたのために、英語論文ですぐ使える表現集を紹介します。大学生から研究者・技術職の方にも役立つ決定版です。世界中の人に使われている本の日本語版です。
アカデミック・フレーズバンク そのまま使える!構文200・文例1900
この本は、ワンパターンな表現を避け、英語らしい英文を書くテクニックが多数載っています。英語の資格試験のライティングセクションや大学の英文レポートが想定されています。著者は翻訳・通訳で活躍されています。
ここで差がつく! 英文ライティングの技術—英語は「I」ではじめるな